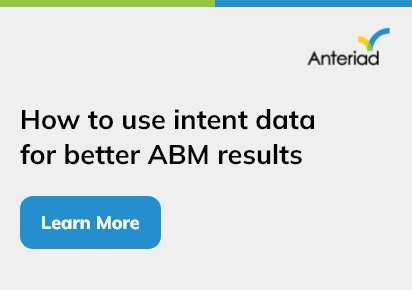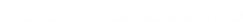1. 「それはITの仕事だ」
多くの公益事業のリーダーは、ビジネスデータ分析を技術的なプロジェクトだと考えます。IT部門に任せてダッシュボードを構築すれば、魔法のようなインサイトが得られる、と。しかし、この考えは、マッキンゼー・アンド・カンパニーが公益事業データに関する記事で指摘した誤解1と全く同じです。
真実はこうです。分析は真空中で行われるものではありません。電力会社では、送電網の信頼性、インフラ、規制圧力、顧客の期待など、様々な要素をバランスよく考慮する必要があるため、運用部門、事業部門、規制当局、そしてIT部門の担当者が一堂に会する必要があります。ビジネスリーダーが分析を「単なるITプロジェクト」のように扱うと、そこから得られる洞察は活用されません。
ビジネスデータ分析を行う際は、ツールを構築するだけでは不十分です。考え方、行動、ビジネスプロセスを変える必要があります。IT部門だけに任せきりにしてはいけません。
2. 「システムは準備万端なので、洞察は流れ出る」
もう一つの大きな誤解は、「これらのシステムはすべて揃っているので、ビジネスデータ分析は自然とうまくいくだろう」というものです。マッキンゼーの例えをもう一度引用すると、多くの公益事業会社はERP、WAM、CIS、GISなどを統合すれば「準備完了」だと考えています。しかし、実際はそうではありません。
ここで問題となるのは、すべてのデータが揃っていても、どのデータがどのような形式で存在するか、どのようにデータがまとめられるか、どのようにクリーンアップされるか、そして人々が使用可能な形式でアクセスできるかどうかについて十分に検討していなければ、ビジネス データ分析は行き詰まってしまうということです。
例えば、レガシーシステムは異なるデータ言語を話す場合があり、サイロ化が続く可能性があります。そのため、公益事業の幹部にとって重要なのは、ビジネスデータ分析を行う際にデータをマッピングすることです。データのソース、フロー、品質、そしてそれらをどのようにリンクさせるかを把握することが重要です。
3. 「データレイクを構築すれば、残りは自然に整理される」
これはおそらく「半ば誤解」と言えるでしょう。多くの組織は、膨大なデータリポジトリ(「データレイク」)を構築すれば、洞察が得られると考えています。しかし、公益事業の世界では、それはリスクを伴います。マッキンゼーの例で言えば、ビジネスコンテキストのない大規模な非構造化データストアは、しばしば高価な「ダークデータ」の墓場となるのです。
ビジネスデータ分析に取り組む際、データレイクは最終目的ではありません。問いかけるべきは、「私たちはどのようなビジネス上の疑問に答えているのか?」「どの分析ユースケースが今、価値を提供しているのか?」です。目的もなくあらゆるデータを投入することは、多くの場合、コスト(ストレージ、複雑さ)を支払い、ほとんど何も得られないことを意味します。
したがって、ユーティリティのコンテキストでビジネス データ分析を計画する場合は、結果から始めて、エコシステムを構築します。
4. 「データの品質と戦略は後回しにできる」
よくあるもう一つの失敗は、データガバナンス、データ品質、そして分析戦略への投資不足です。業界横断的な調査によると、明確な計画なしにデータ分析に着手した企業は、時間とリソースを無駄にし、信頼を失うことが多いことが分かっています。
公益事業では、数百、数千ものセンサー、フィールドデバイス、スマートメーターからデータが生成されることが多く、それらはすべて異なるプロトコルと品質を備えています。ここでのビジネスデータ分析の価値は、信頼できるデータ、構造化されたプロセス、そして優れたガバナンスにかかっています。
これを省略すると、分析によって疑わしい結果(「ゴミを入れればゴミが出る」)がもたらされ、リーダーシップは信頼を失ってしまいます。
5. 「サイロ化は問題ではありません。各部門が独自の分析を行うことができます」
公益事業の世界では、発電、配電、顧客サービス、規制、運用といった様々な事業部門が、それぞれ独自の分析やデータレポート作成業務を行っていることがよくあります。しかし、サイロ化が進むと、企業全体のビジネスデータ分析への取り組みは断片化されてしまいます。エネルギー/公益事業の分析という観点から見ると、データサイロは大きな障害となります。
部門Aと部門Bがそれぞれ独自のニッチな分析に取り組んでいて、データ戦略を共有していない場合、分野横断的なインサイトは失われます。例えば、顧客の使用パターンとグリッド資産の状態データを関連付けることで、新たなメンテナンスの優先順位が明らかになるかもしれません。しかし、これらが別々のサイロに分散していると、全体像を把握することはできません。
したがって、公益事業会社の幹部は、部門ごとではなく、企業全体でビジネス データ分析の取り組みを調整するよう推進する必要があります。
5.5. 「投資さえすれば、アナリティクスのROIはすぐに得られる」
「半分」の項目はこうです。分析ツールに投資し、データサイエンティストを雇えば、すぐに大きな利益が得られるという期待や信念があります。しかし、現実は一様ではありません。あるブログでは、大企業が分析関連のサポート体制への投資不足に陥っており、それがプロジェクトの失敗につながっていると指摘されています。
特に公益事業の分野では、複雑なシステム、レガシー資産、規制上の制約、そして長期サイクルの投資といった課題に直面します。そのため、ビジネスデータ分析は、「短期的な成果」と長期的な視点の両方を考慮した設計をしない限り、必ずしも短期的な成果をもたらすとは限りません。
解決策:明確な指標を持つ、影響度の高いユースケース(例えば、予知保全や需要予測など)を1つか2つ選びます。そして、段階的に導入を進め、価値を示し、拡張していきます。「3ヶ月で分析機能を使って全てを刷新する」などと、大げさに賭けるのはやめましょう。
すべてをまとめる
公益事業の経営幹部がビジネス データ分析を単なるチェックボックス(「分析を実装しましょう」)として捉えると、多くの場合、次のような罠に陥ります。IT 部門に任せきりにする、システムだけで実現できると思い込む、ビジネス上の質問よりも先にデータ レイクを構築する、データ ガバナンスを無視する、サイロを容認する、すぐに ROI が得られると期待する、といった罠です。
代わりに、より良いパスは次のようになります。
•定義:どのようなビジネス成果を目標としているのか? (例: 停止時間を 15% 短縮、顧客エクスペリエンス評価の向上、資産ライフサイクル コストの最適化)。
•調整:ビジネス リーダーシップ、運用、IT、分析の各チームを連携させます。ビジネス データ分析は部門横断的なものです。
•インベントリ:すでに持っているデータ、その保存場所、データのクリーン度、アクセス可能性をマップします。
•目的意識を持って構築する:重要なユースケースを選択し、システムを連携させ、データをクリーンアップし、ガバナンスを確保します。
•測定:分析導入指標 (誰がインサイトを使用しているか) とビジネス指標 (何が改善されたか) の両方の指標を初日から追跡します。
•スケール:成功が明らかになったら、より多くのドメイン、単なる記述的分析ではなくより高度な分析 (予測的/処方的) に拡張します。
•繰り返し:ビジネス データ分析は一度で完了するものではありません。データは進化し、ビジネスは成長し、分析の成熟度も進化する必要があります。